
本年も皆様の歴史づくりに邁進します
平素は格別のお引き立てを賜わり、心より感謝申し上げます。
皆様の伝えたい気持ちに対する情熱とお力添えにより、新しい年に邁進することができました。
昨年もいろいろありましたが、多くのお客様と紙面を通じた交流をさせていただきました。広報紙の役目を充分に果たせるよう、本年も編集の技術をさらに磨き、全力で皆さまをサポートいたします。
本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。


平素は格別のお引き立てを賜わり、心より感謝申し上げます。
皆様の伝えたい気持ちに対する情熱とお力添えにより、新しい年に邁進することができました。
昨年もいろいろありましたが、多くのお客様と紙面を通じた交流をさせていただきました。広報紙の役目を充分に果たせるよう、本年も編集の技術をさらに磨き、全力で皆さまをサポートいたします。
本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

フジイ企画社報『紙ブログ』2026年新春号発行のお知らせです。例年通り、秋頃からは年末号に向けた広報紙の制作に取り組んでいました。新年からも、心に残る紙面づくりのお手伝いができるよう取り組んでまいります。
さて今回も、AI男女によるこの「紙ブログ62号」の音声解説を添付しました。まだまだAIは進化途上で、有名な歴史上の人物(楠木正成)も読み間違えていて、3面の「私の休憩室」の解説部分はカットしました。また本文でお読みください。
納品後、お客様にはアンケートをお渡ししております。紙面について、ご感想やご要望などありましたらぜひお聞かせください。
社報『紙ブログ』は無料でお送りします(PDFも可)。メールフォーム等にて連絡先・氏名と「紙ブログ希望」とお書きください。
『紙ブログNEWS』2026年新春号(第62号)contents
1面 創造性が退化する概念化された言葉
2面 【製作部あれこれ=連載25】トップ記事の選び方
3面 【私の休憩室】(スタッフコラム) 【私の一枚】スタッフの写真コーナーです
4面 【季節のあしあと】
(タイトル写真)大阪府立桜和高等学校PTA広報の企画会議
 どの記事をトップにするか?
どの記事をトップにするか?
どのページに何の記事を載せるかという「紙面割り」は、お客様から指定いただくことが多いのですが、逆に記事だけ頂いて、その割り振りのほとんどをお任せいただくことも、よくあります。
こうしたとき、まず最初の難問は「どの記事をトップ(一面目)にするか?」ということです。
定番記事が多くても新鮮な紙面への工夫
会話や文章でも「一番最初に何を伝えるか」を悩むことがありますが、紙面づくりも同様に「トップに何を置くか」を決めるのは、紙面全体の印象を決めることにもなるので結構難しく、奥深い作業です。
機関紙などでは毎年定番の行事が多いので、どうしても前回同時期を踏襲して、紙面が似たような印象になりがちなことが、皆様も悩まれている課題の一つです。
読者目線を感じる紙面づくりを…
ここで最初に意識した方が良いのは、「読者の視点」です。読んでもらいたい記事の優先順位と、読者の反応は違うという認識を持つことです。
恒例行事でも、必ずトップで扱うという固定観念は本当は必要ではなく、これまでの全体の人の動きを見て、その流れを見つけ出すことが紙面割りの指標になります。ただ、前例の踏襲をやめて切り口を変えるのは、編集者にとっては結構勇気が要ることではあります。
読者を引きつける重要な役割
一面トップは、紙面を手に取ったとき、読者が一番最初に目にする広告塔のようなもの。ここに載せる記事のインパクト次第で、次ページ以降の反応が変わってくることも多いです。
トップ記事を決める時、記事内容や写真、他の記事とのバランスなど判断基準はいくつもありますが、やはり決め手となるのは「読者の視点」。「もし私が一読者だったら…」という基準を、いつも意識しておくと良いかもしれません。
どんな記事にもそれぞれ書いた人の想いが詰まっていて、紙面割りは広報担当の皆様にとっても頭を悩ませるところかと思います。発行者・執筆者・読者の見方は違うということを理解して、橋渡しをするのが編集者の仕事です。
(社報『紙ブログNEWS』2026年新春 第62号)

フジイ企画社報『紙ブログ』2025年秋号発行のお知らせです。長かった夏も終わり、ようやく秋らしくなってきました。これから行事が増えてくる季節となりますが、引き続きお客様をサポートできるよう取り組んでまいります。
第61号〝音声解説〟へのコメント
今回も、解説のAI音声ファイルを最下段(↓)にアップしました。今回で4号分アップしていますが、漢字の読み間違い、特に固有名詞の読み間違いが今も多いでご了承下さい。AIへはプロンプトを変えて何度も生成し直しているのですが、まだ覚えが悪いですね((´∀`))。
1面代表の巻頭言「ことばの創造性②」の記事に「言霊」のことを書いているのですが、AIは〝いきたま〟と呼んでいます。正しくは〝ことだまです〟他にもあるのですが、これはちょっと意味が通じないので予め訂正しておきます。またご感想をよろしくお願いします。
なお、お客様には、品後アンケートをお渡ししております。紙面について、ご感想やご要望などありましたらぜひお聞かせください。
社報『紙ブログ』は無料でお送りします(PDFも可)。メールフォーム等にて連絡先・氏名と「紙ブログ希望」とお書きください。
『紙ブログNEWS』2025年秋号(第61号)contents
1面 身体と一体となる豊かな“自己表出”
2面 【製作部あれこれ=連載24】色合わせの奥深さ
3面 【私の休憩室】(スタッフコラム) 【私の一枚】スタッフの写真コーナーです
4面 【季節のあしあと】7~8月の活動写真アルバムです
(タイトル写真)大阪府教育センター附属高等学校PTA広報委員さんと担当の先生(探究図書室で)
紙ブログ第61号の音声解説
なお、今回もAIによる社報『紙ブログ』紙面内容の音声解説アップしました。男女二人の対話形式で紙面の内容を紹介です。一度ご視聴下さい。
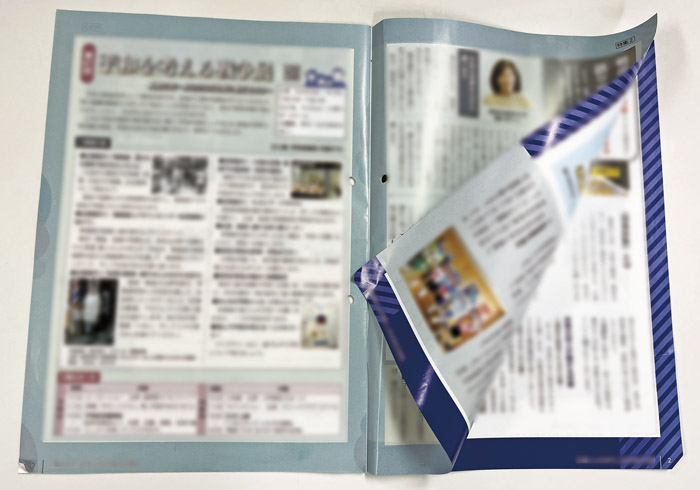
日頃よく発生する「色が違う」問題
カラー印刷が主流になった今、お客様自らPC画面やカラーチャートで確認して色データを作ったつもりでも、刷り上がってみると「イメージが違う」と言われることがよくあります。
弊社では、まず元データの確認、その後にプロセスカラー出力版の点検を行います。基本的にはお客様が指定した色の数値が自動変換されているので、作成した人の入力ミスがない限り、この一連の工程での不具合は稀です。
次に大切なのが紙による〝色校正〟ですが、この時点で、お客様の思っている最終イメージ通りではないケースが結構あります。
ほぼデジタルで自動的にやっているように見えるこの業界ですが、最終製品は、用紙の種類や厚みの違い、最後は印刷オペレータによる〝色校正〟の解釈の現場判断に、個性の違いが出てきます。弊社はそれを総合的に判断して指示・制作にあたります。
データは問題ないのに色が変わる?
ところで最近、色校正を確認いただいたお客様から、「左右のページで色が違う」というご相談がありました。言われてみれば、視覚的に違うような気がしてデータを再確認してみたのですが、左右の色合いは1%の違いもありませんでした。
少し悩みましたが、「色が違って見えた」原因は、右ページの真裏のページでは濃い青色を使っており、その色が影響(裏うつり)していたためでした。分かってみれば単純な理由だったのですが、色の見え方の違和感を迅速に〝裏うつり〟の可能性として見抜くためには、日頃から様々な角度で印刷物に触れて、地道に経験を重ねることが大切だと感じました。
地道な試行錯誤で「勘」を掴んでいく
このようにデータに問題が無くても、条件によって仕上がりが思った通りにならないことは、日常茶飯事です。なので、「印刷機種」「印刷用紙の種類」「印刷オペレータの個性」など様々な要因を勘案する必要があります。何度も印刷を経験することで「勘」が掴めたら、再現が難しい色も感覚的に分かるようになっていきます。ある程度仕上がりを予想して、色合いを決めることができるスキルが身に付きます。
印刷物づくりの奥深さを更に実感
つまり、デジタル技術が発達した現代であっても、印刷実務は現場の人間の「経験と勘」によるところも大きいように思います。ですが、これがものづくり(クリエイション)の面白さのひとつかもしれません。印刷物の奥深さをより一層感じる一件となりました。
(社報『紙ブログNEWS』2025年秋 第61号)

暑中お見舞い申し上げます
短い梅雨を過ぎた6月後半から、いきなり猛暑の日々が続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか
弊社のお客様は、夏の特集に向けての作業が急ピッチで続けておられます。フジイ企画社報『紙ブログ』2025年夏号号も、そんな合間を縫ってようやく発行になりました。今後もお客様のサポートできるよう取り組んでまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
納品後、お客様にはアンケートをお渡ししております。紙面について、ご感想やご要望などありましたらぜひお聞かせください。
社報『紙ブログ』は無料でお送りします(PDFも可)。メールフォーム等にて連絡先・氏名と「紙ブログ希望」とお書きください。
紙ブログ第60号の音声解説
なお、今回から実験的にAIによる社報『紙ブログ』紙面内容の音声解説アップしました。男女二人の対話形式で紹介しています。一度ご視聴いただければ紙面の内容が簡単にわかります。
『紙ブログNEWS』2025年新春号(第58号)contents
1面 内側から湧き出る思い言葉で紡ぐ
2面 【製作部あれこれ=連載22】ページ数が多く納期が短い冊子の制作術
3面 【私の休憩室】(スタッフコラム) 【私の一枚】スタッフの写真コーナーです
4面 【季節のあしあと】
(タイトル写真)羽曳が丘小学校PTA役員さん
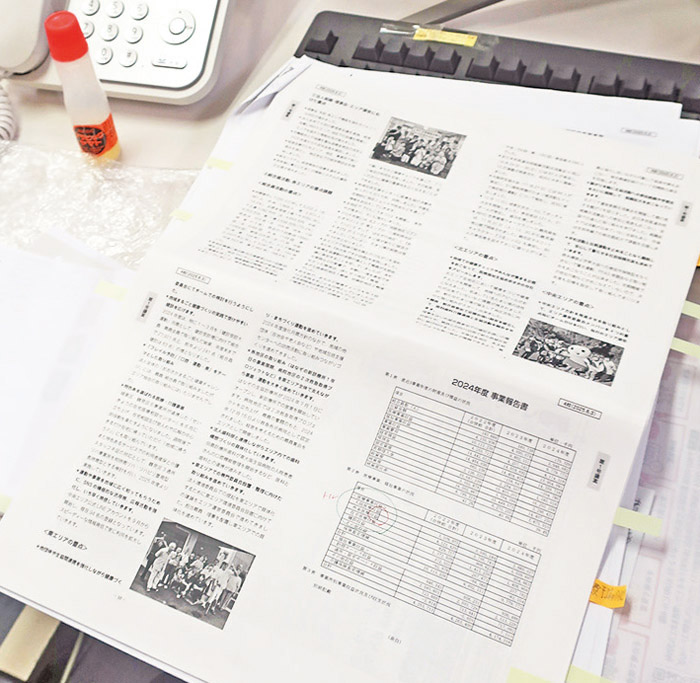
広報紙と共通する時事冊子の即応体制
通例の広報紙制作と併行して、少しスパンの長い“頁物(ページもの)”の編集も、弊社では大事な業務になります。
“頁物”は、作業内容から「書籍」と「冊子物」とに大別しているのですが、今回は「冊子物」についてお話しします。
主に報告集、記録集、議案書などページ数や文章・写真等の使用点数が多く、しかも執筆者に複数人が関わる印刷物を「冊子物」と呼んでいます。
〝納期圧縮〟は最新記事を掲載するため
他の“頁物”との一番の違いは、一般書籍より『納期が短い』という点につきます。報告集、記録集、議案書は広報紙のような時事出版物に近く、①できる限り最新の情報を掲載するので入稿時期が遅くなる一方、②成果物を一斉に使用(集会など)するため動かせない日程があり、また配布の都合上、納期は逆に前倒しになる傾向にあるので、工程をどれだけ短縮できるかがネックになります。
一般に“頁物”の場合は、社内の編集・制作期間だけでなく、印刷・製本・仕分けなどの下流工程でも時間を要するので、三者で綿密に打ち合わせをして工程表を取り交わしていきます。ただ、このような冊子の場合、期日があっても、会議での合意が無ければ進められない内容の記事もあり、全てが工程表通りには進みません。
全ページの進捗が分かる工程表の工夫
弊社では広報紙制作を主流としているため、工程表の合意と交換は、冊子制作に限らず全てのお客様と取り交わしています。これは他の業務が集中しても個別のお客様にご迷惑をかけないための基本体制で、お客様ごとの工程表を集約し、毎朝の社内ミーティングで確認しています。
ページ数の多い冊子の場合は、このほかに校了後点検の時間短縮のために、校了以前の制作期間で「入稿状況表」を作成します。全記事一覧と入稿・差替日を入稿のたびに追記し、弊社とお客様とで都度交換し合うようにします。どのページが未入稿なのか、いつ差替になったのかがひと目で分かるよう管理しています。
品質力を強化する校了後の再点検
通常、冊子は100~200ページもあるので、内校(社内校正)も念入りに行う必要があります。内校のポイントは、主にデータ上の不備だけでなく、記事内容のチェックも行います。記事内容の校正については基本的にお客様側の責任ではありますが、ミスによる損失は責任の所在に関係なく信頼関係にも影響するため、校正ミスと判断できるものはご連絡および再提案を密にさせていただいています。品質力強化が弊社の最大の目的です。
(社報『紙ブログNEWS』2025年夏 第60号)

紙ブログ第59号の音声解説
なお、第58号から実験的にAIによる社報『紙ブログ』紙面内容の音声解説アップしました。男女二人の対話形式で紹介しています。一度ご視聴いただければ紙面の内容が簡単にわかります。
『紙ブログNEWS』2025年新春号(第58号)contents
1面 自分軸を生きると人生が動き始める
2面 【製作部あれこれ=連載22】画面と印刷の色の違い
3面 【私の休憩室】(スタッフコラム) 【私の一枚】スタッフの写真コーナーです
4面 【季節のあしあと】
(タイトル写真)大阪府立市岡高校PTA広報委員会
 刷り上がった紙面の「色が違う」!?
刷り上がった紙面の「色が違う」!?
多くの団体が年度末号の広報紙を発行する2~3月。お客様にとってこの時期は、これまで数回の校正のやり取りを経て、刷り上がった紙面をしみじみ見直す時。すると、「校正時と比べて色がくすんで見える」ということがよくあります。
近年、ゲラ刷り校正のやり取りは、電子メールなどネット経由で送受信することが通常となってきました。
本来はこれをプリントアウトして確認するのが通常作業なのですが、お客様が多忙であったり、予算の面も考えて、画面上で処理することが多いです。
パソコン画面と印刷物の色の表現の違い
そもそも、この発色の違いは、色の表現方法に違いがあるからです。まず画面(パソコンやスマホなど)はレッド、グリーン、ブルー(RGB)の「光の三原色」を組み合わせて色が表現されるので、明るく鮮やかに見えます。
一方、印刷物はシアン、マゼンタ、イエローの「色の三原色」と黒を交えた(CMYK)インクを重ね合わせた4色で表現され、RGBに比べて表現できる色域が狭く、特に鮮やかな青や緑、蛍光色などは印刷では再現しにくくなります。
この表現方法の違いにより、印刷時に色が沈んで見えることがあります。
こだわりたい場合は「色校正」でチェック
この補正は結構専門的で、弊社では使う用紙や印刷機などを予め勘案し、ある程度仕上がりを予測しながら補正もしています。
写真集や画集、商品パンフなどの〝ビジュアルが命〟の制作物を手掛ける時は、「色校正」という、いわゆる試し刷りの工程を加えて色合いの細部を確認していきます。大きく分けて、本番と同じ環境と同じ用紙で印刷する「本機色校正」、高精度なプリンタで印刷する「簡易色校正」の2種類があります。用紙の種類によって発色に違いが出てくるので、仕上がりの印象も確認することができます。ただし、色校正は時間と費用が結構掛かります。
印刷物ごとに合わせた色調調整を
通常の広報紙制作では、色校正まではあまり行わないのですが、弊社では画面の見た目だけではなく、お客様の使われる紙質を考えて、刷り色の色調、彩度などを微妙に調整しています。それでも印刷・製版オペレーターによっても変わってくるので、まだまだ研究の余地があると感じています。
写真=印刷前に「色校正」紙を出して刷色をチェック。
(社報『紙ブログNEWS』2025年春 第59号)

平素は格別のお引き立てを賜わり、心より感謝申し上げます。
皆様の伝えたい気持ちに対する情熱とお力添えにより、新しい年に邁進することができました。
昨年中は、多くのお客様と紙面を通じた交流をさせていただきました。広報紙の役目を充分に果たせるよう、本年も編集の技術をさらに磨き、全力で皆さまをサポートいたします。
本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。