デジタル時代こそ 「経験と勘」が大事
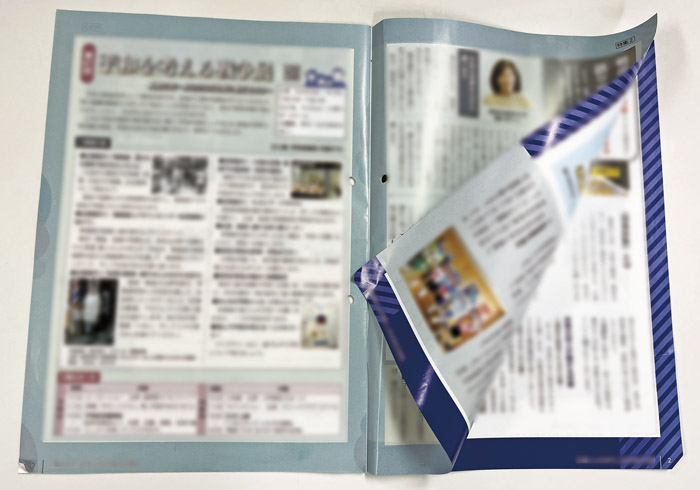
日頃よく発生する「色が違う」問題
カラー印刷が主流になった今、お客様自らPC画面やカラーチャートで確認して色データを作ったつもりでも、刷り上がってみると「イメージが違う」と言われることがよくあります。
弊社では、まず元データの確認、その後にプロセスカラー出力版の点検を行います。基本的にはお客様が指定した色の数値が自動変換されているので、作成した人の入力ミスがない限り、この一連の工程での不具合は稀です。
次に大切なのが紙による〝色校正〟ですが、この時点で、お客様の思っている最終イメージ通りではないケースが結構あります。
ほぼデジタルで自動的にやっているように見えるこの業界ですが、最終製品は、用紙の種類や厚みの違い、最後は印刷オペレータによる〝色校正〟の解釈の現場判断に、個性の違いが出てきます。弊社はそれを総合的に判断して指示・制作にあたります。
データは問題ないのに色が変わる?
ところで最近、色校正を確認いただいたお客様から、「左右のページで色が違う」というご相談がありました。言われてみれば、視覚的に違うような気がしてデータを再確認してみたのですが、左右の色合いは1%の違いもありませんでした。
少し悩みましたが、「色が違って見えた」原因は、右ページの真裏のページでは濃い青色を使っており、その色が影響(裏うつり)していたためでした。分かってみれば単純な理由だったのですが、色の見え方の違和感を迅速に〝裏うつり〟の可能性として見抜くためには、日頃から様々な角度で印刷物に触れて、地道に経験を重ねることが大切だと感じました。
地道な試行錯誤で「勘」を掴んでいく
このようにデータに問題が無くても、条件によって仕上がりが思った通りにならないことは、日常茶飯事です。なので、「印刷機種」「印刷用紙の種類」「印刷オペレータの個性」など様々な要因を勘案する必要があります。何度も印刷を経験することで「勘」が掴めたら、再現が難しい色も感覚的に分かるようになっていきます。ある程度仕上がりを予想して、色合いを決めることができるスキルが身に付きます。
印刷物づくりの奥深さを更に実感
つまり、デジタル技術が発達した現代であっても、印刷実務は現場の人間の「経験と勘」によるところも大きいように思います。ですが、これがものづくり(クリエイション)の面白さのひとつかもしれません。印刷物の奥深さをより一層感じる一件となりました。
(社報『紙ブログNEWS』2025年秋 第61号)

